AWSは何がすごい?活用事例や役立つ資格を紹介
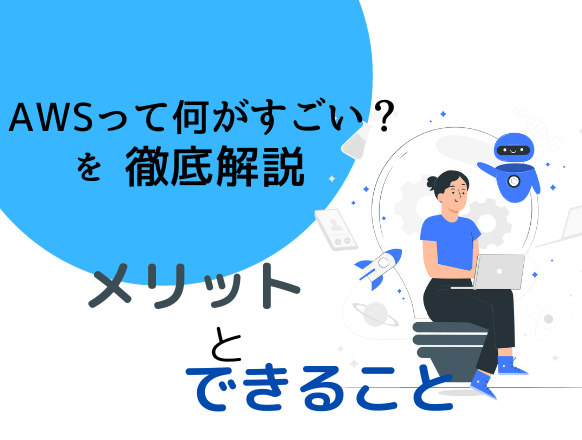
AWSとは、クラウドベースでシステムを開発したり、Webサイトを運用・監視したりすることができるサービスです。
本記事では、AWS(Amazon Web Services)を利用するメリットや、活用事例をご紹介します。
そのほか、AWSを利用するときの注意点もお伝えするので、メリットだけではなくデメリットも理解したうえで利用するか判断すると良いでしょう。
AWSとは?
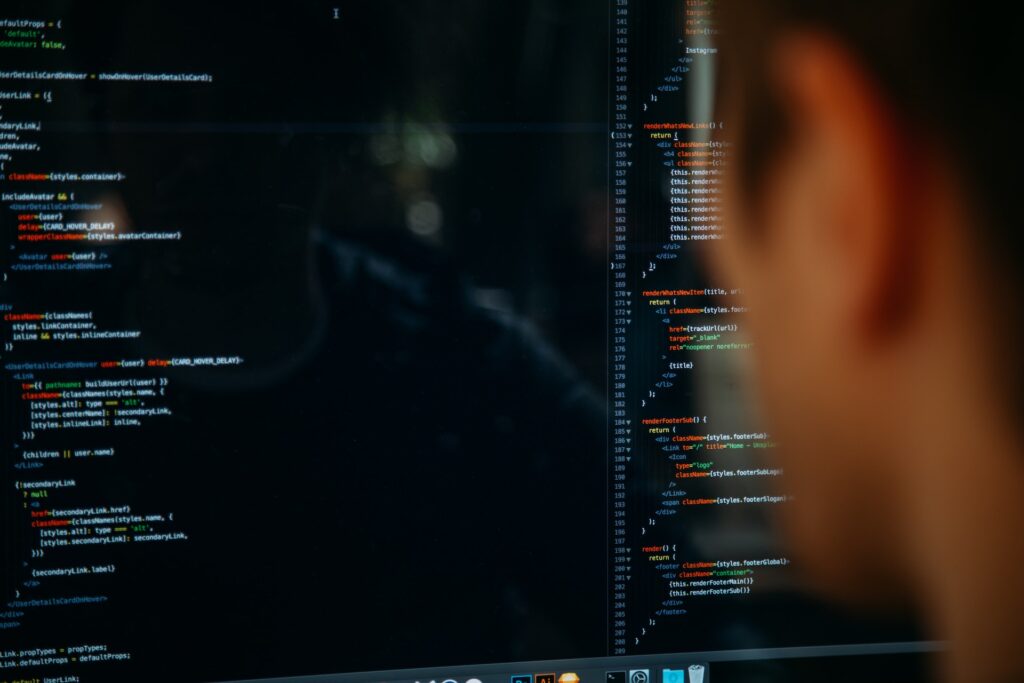
AWS(Amazon Web Services)は、Amazonが提供するクラウドコンピューティングプラットフォームです。
インターネットを通じてサーバー、ストレージ、データベース、ネットワーキング、ソフトウェアなどのコンピューティングリソースを提供しています。
ハードウェアの設置や管理が不要で、オンデマンドでリソースを拡張・縮小できるため、効率的かつ柔軟なシステム運用が可能です。
多種多様なサービスを提供しており、Webサイトのホスティングからビジネスアプリケーションの運用、ビッグデータの分析、AIの活用まで幅広く対応しています。
AWSは何がすごい?メリットを紹介

ここでは、AWSの何がすごいのか、メリットを8つご紹介します。
初期費用をかけずに構築することも可能
AWSは従来のオンプレミスシステムと違い、サーバーやインフラストラクチャを購入・設置する必要がなく、無料枠内であれば、初期費用がかからず構築が可能です。
ビジネスの成長や需要の変化に応じて、必要なリソースを追加・削減できるので、必要以上のリソースに対する投資を避けられるでしょう。
またインフラの設置や設定にかかる時間もかからないので、プロジェクトを迅速に開始できます。
グローバル展開ができる
AWSは、世界中に多数のリージョンとアベイラビリティゾーンを持っており、各地域の顧客に近い場所でサービスを提供することができます。そのため、世界各地でビジネスやサービスを迅速かつ容易に展開しやすいです。
サービスやアプリケーションをユーザーに近いデータセンターでホストすることで、応答時間を短縮し、ユーザーエクスペリエンスを向上させることができます。
また、異なる国や地域の法律や規制に準拠しながらサービスを提供することが可能です。複数のリージョンにデータを分散することで、災害や障害が発生した場合のリスクを軽減し、高い可用性を確保できるでしょう。
運用コストを最適化できる
AWSの柔軟な料金体系とスケーラブルなリソース管理により、企業が自身の使用状況に応じてコストを効率的に管理できます。
AWSでは、インフラを事前に購入・設置する代わりに、必要なリソースをオンデマンドで利用し、使用した分のみ料金を支払います。これにより、未使用リソースに対するコストが発生しません。
トラフィックや処理負荷に応じてリソースを自動的にスケーリングできるため、ピーク時にはリソースを増やし、需要が低い時は減らすことでコストを抑えることが可能です。
また、長期間安定してリソースを使用する場合の予約インスタンスや、一時的な余剰コンピューティング容量を低価格で利用できるスポットインスタンスなど、さまざまな料金オプションを活用することで、さらなるコスト削減が実現できるでしょう。
運用負荷を軽減する
AWSはクラウドベースのサービスを通じて、インフラストラクチャの管理や保守に関連する作業負担を大幅に減らすことができます。具体的には、ハードウェアの故障対応やアップグレードなどの作業を行う必要がなくなります。
AWSでは多くの運用プロセスを自動化することが可能で、統合管理ツールを利用して簡単にシステムを監視、管理できるでしょう。
ビジネスの成長や需要の変動に応じて、リソースを柔軟にスケールアップまたはダウンできます。運用上の負荷とコストを最適な状態に保つことが可能です。
セキュリティが高い
AWSが提供するクラウドサービスは、高いセキュリティ基準とプロトコルに基づいて運用されています。
AWSはデータセンターのセキュリティ、ネットワークセキュリティ、システムセキュリティなど、多層にわたる包括的なセキュリティ対策を講じています。インフラストラクチャを24時間365日監視し、セキュリティの脅威に対する自動化された対応を行っています。
データは転送中および保存中に暗号化され、不正アクセスやデータ漏洩のリスクの低減が可能です。多数の国際的なセキュリティ基準とコンプライアンス要件を満たしており、特定の業界や規制に適応する認証を取得しています。
日本語でのサポートに対応している
AWSの技術サポートチームは日本語でのサポートを提供し、技術的な問題や運用に関する疑問に対応します。日本語のドキュメント、ガイド、チュートリアルを豊富に提供しており、日本人でも十分に理解しながらの利用が可能です。
日本国内のAWSユーザー同士で情報交換や相互支援が行えるコミュニティやフォーラムが存在し、利用者間のコミュニケーションが促進されるでしょう。日本語でのトレーニングプログラムやセミナーを定期的に開催し、最新のクラウド技術やベストプラクティスを学ぶ機会を提供しています。
柔軟にサービス内容を拡大・縮小できる
AWSは、ビジネスのニーズや要求に応じて容易にリソースを調整できます。たとえば、トラフィックが増加した場合、追加のコンピューティングリソースやストレージの調整が可能です。
リソースの使用量に基づいて支払いが行われるため、無駄なコストを削減し、必要なサービスに対してのみ費用を支払うことができます。
サービスのラインナップが豊富である
AWSが提供するサービスは、200を超えるほど種類が豊富です。幅広い種類のクラウドサービスやツールから、自社に合ったものを選ぶことができます。
コンピューティングやストレージ、データベースネットワーキングなどのサービスがあります。なかには、開発者ツールや機械学習などのサービスもあるので、新たにシステム開発を考えている企業も活用できるでしょう。
AWSで何ができる?

ここでは、AWSでできることを6つご紹介します。
サーバー環境の構築・運用
AWSでは、クラウド上に仮想サーバーを設置し、管理・運用することができます。AWSのEC2(Elastic Compute Cloud)サービスを使用すれば、必要なスペックやOSを選択し、仮想サーバーインスタンスを数分で立ち上げられます。
Elastic Load Balancing(ELB)を使用すると、複数のサーバー間でトラフィックを均等に分散が可能です。その結果、システムの可用性と耐障害性が向上するでしょう。
また、AWS Auto Scalingを用いてサーバーの数を自動的に調整したり、Amazon S3やAmazon EBSのスナップショット機能を活用してデータのバックアップなどを行うことも可能です。
データ保存やコンテンツ配信
AWSのクラウドストレージサービスとコンテンツ配信ネットワーク(CDN)を利用して、データを安全に保存し、効率的にユーザーに配信することができます。
データ保存では、任意の量のデータを保存できるAmazon S3(Simple Storage Service)を活用できます。高い耐久性と拡張性を備えており、バックアップ、アーカイブ、ビッグデータ分析などに広く利用されています。
また、Amazon EBS(Elastic Block Store)は、EC2インスタンスに接続するためのブロックレベルのストレージサービスです。永続的なストレージニーズに対応し、データベースやアプリケーションサーバーのストレージとして活用できます。
コンテンツ配信では、Webサイトやアプリケーションのコンテンツをエンドユーザーに高速で配信できるAmazon CloudFrontが便利です。世界中に分散されたエッジロケーションを利用し、ユーザーに近い場所からコンテンツを提供することで、レイテンシを大幅に削減できるでしょう。
データベース
AWSをデータベースとして活用することで、クラウド上でデータベースを構築、管理、運用が可能です。
データベースとして活用するときに便利なサービスは、以下のとおりです。
- Amazon RDS(Relational Database Service)
- Amazon DynamoDB
- Amazon Aurora
- Amazon Redshift
- Amazon Elasticache
Amazon RDS(Relational Database Service)は、MySQL、PostgreSQL、MariaDB、Oracle、Microsoft SQL Serverなど、一般的なリレーショナルデータベースを簡単にセットアップ、運用、スケールできるサービスです。
Amazon DynamoDBは、完全にマネージドなNoSQLデータベースサービスです。大規模なスケールでのワークロードにも対応可能で、柔軟性と高いパフォーマンスを提供します。
Amazon Auroraは、MySQLおよびPostgreSQLと互換性のある、高性能なリレーショナルデータベースです。商用データベースのパフォーマンスと単純さを低コストで提供します。
Amazon Redshiftは、データウェアハウジングサービスです。大量のデータに対する高速な分析クエリと複雑なデータ分析を可能にします。
Amazon Elasticacheは、RedisやMemcached互換のインメモリデータストアを提供するサービスです。データベースレイヤーのキャッシングによってパフォーマンスを向上させます。
システム開発
AWSは、システム開発ができるツールを多数提供しています。
具体的には、ソースコードの管理ができるAWS CodeCommitや、ビルドサービスであるAWS CodeBuild、などがあります。
AWSの開発ツールを活用することで、CI/CD(継続的インテグレーション/継続的デリバリー)パイプラインの構築が可能です。
loTソリューションの構築
AWSが提供する各種クラウドサービスを活用して、インターネットに接続されたデバイス(IoTデバイス)向けのアプリケーションやシステムを開発・管理できます。
AWS IoT Coreを使用して、数百万のデバイスを安全に接続し、簡単に管理することができます。このサービスを通じて、デバイスからデータを収集し、クラウドへ送信することが可能です。
収集したデータは、AWSのデータ処理と分析サービス(Amazon KinesisやAmazon S3など)を使用して処理・分析されます。リアルタイムのインサイトを得たり、データ駆動型の意思決定をサポートしたりすることが可能です。
AI機能の活用
AWSでは、AIおよび機械学習サービスを用いて、アプリケーションに高度な分析や知能的な機能を組み込めます。
AI機能を提供しているAWSサービスは、以下のとおりです。
- Amazon SageMaker
- Amazon Rekognition
- Amazon Polly
- Amazon Lex
- Amazon Comprehend
Amazon SageMakerは、機械学習モデルの開発、トレーニング、デプロイを容易にするフルマネージドサービスです。開発者とデータサイエンティストが迅速に機械学習モデルを構築し、運用スケールで展開できます。
Amazon Rekognitionは、画像認識やビデオ分析を提供するサービスです。顔認識、オブジェクト検出、テキスト抽出などができ、メディアファイルからの洞察を自動的に得ることができます。
Amazon Pollyは、テキストを自然な発話に変換するテキスト音声変換サービスです。多様な言語やアクセントに対応しており、アプリケーションに音声機能を追加できます。
Amazon Lexは、チャットボットを簡単に構築できるサービスです。自然言語理解(NLU)と自動音声認識(ASR)技術を活用して、対話型インターフェースを提供します。
Amazon Comprehendは、自然言語処理(NLP)を利用してテキストデータから洞察を抽出するサービスです。感情分析、キーワード抽出、エンティティ認識などが可能です。
AWSを利用する際のデメリット

ここでは、AWSを利用する際のデメリットを4つご紹介します。
1. 従量課金制で月々の料金が変動する
AWSは従量課金制を採用しており、使用した分だけ料金が発生する仕組みです。
料金体系には柔軟性がある一方で、月々の料金が変動しやすいというデメリットがあります。
使用したリソースに応じて課金されるため、トラフィックやアクセス数の増減、ストレージの利用増、データ転送量、オンデマンド vs リザーブドインスタンスなどが要因で変動します。
AWSはリソースを動的にスケールできるため、意図せずリソースが増えてしまうことがあり、予算の管理が複雑です。
開発環境で使ったEC2インスタンスを停止し忘れ高額な請求が発生する、一時的なトラフィック増加でAuto Scalingが働きインスタンスが増加して料金が急上昇する、などのケースがあります。
AWSの利用状況を細かく監視していないと、気づかないうちに高額請求が発生するリスクがあります。
無料枠を超えていることに気づかなかったり、サイバー攻撃などでトラフィックが急増したりする恐れがあるでしょう。
2. カスタマイズの自由度が低い
AWSはクラウドサービスとして強力なインフラを提供していますが、オンプレミス環境と比較するとカスタマイズの自由度が低い点がデメリットです。
オンプレミス環境では、サーバーのCPU、メモリ、ストレージ、ネットワーク機器などを自由に選択・構成できますが、AWSではAWSが提供するインスタンスやストレージの種類の中から選ばなければいけません。
AWSではVPCを利用してネットワークを構築できますが、独自のネットワーク機器の利用不可、ネットワーク帯域の制限、OSやソフトウェアの制限などが生じます。
3. メンテナンス時の対応方法を決めておく必要がある
オンプレミス環境では自社でメンテナンスのタイミングを調整できますが、AWSではAWSの都合でメンテナンスが実施されるため、適切な対応をしないとシステムに影響が出る可能性があります。
AWSは定期的にハードウェアの交換、セキュリティアップデート、サービスのアップグレードを行っており、ユーザー側で完全に制御できません。
AWSを利用していると、ユーザー自身が定期的にメンテナンスすべき項目もあります。
EC2で運用しているLinuxやWindowsのOSは、AWSでは自動更新されないため、ユーザー側でメンテナンスが必要です。
AWSのサービス更新によって、一部のAPI仕様が変更されるケースもあります。
アプリケーションの動作確認を定期的に行わないと、突然システムが動かなくなるリスクがあるので注意しましょう。
4. サービスが多すぎる
AWSには、同じような機能を持つサービスが複数存在するため、どれを選べば最適なのか判断が難しい場合があります。
AWSは毎年新しいサービスを追加し、既存のサービスも頻繁にアップデートされるため、学習し続けなければならない負担があります。
また、AWSは従量課金制ですが、サービスごとに料金体系が異なり、コスト計算が難しいという問題が挙げられるでしょう。
同じストレージでも、用途やアクセス頻度によって料金が異なり、適切な選択をしないとコストが増大する可能性があります。
AWSの各サービスは連携できるように設計されていますが、適切に統合しないと運用管理が複雑になり、システムが混乱する場合があるでしょう。
どのログをどのサービスで管理すべきか、統一的な戦略を持たないと運用が煩雑になってしまいます。
AWSは何に使われている?活用事例を紹介
ここでは、実際にAWSを導入している企業を5社ご紹介します。
事例1. 株式会社ソラコム
株式会社ソラコムは、AWSのマネージドサービスを活用して、ローコードで生成AIを使ったIoTアプリケーションを開発できる「SORACOM Flux」を提供中です。
SORACOM Fluxにより、開発期間が数か月から数日へと短縮され、製造業、物流業、小売業を中心に高い関心を集めています。
SORACOM Fluxは、AI活用のハードルを下げ、迅速に高度な分析を導入できるため、開発スピードが向上し、運用コストの削減にも貢献しています。
また、安定したサービス提供により、管理者はアプリケーションの運用に集中でき、運用負荷の軽減も実現しました。
事例2. 株式会社ネイティブキャンプ
オンライン英会話サービスのネイティブキャンプは、Amazon Bedrockを活用して「AIトピックサジェスト機能」を開発しました。
AIトピックサジェスト機能は、会員のプロフィールに基づいて最適なトークテーマを提案し、講師の負担を軽減する機能です。
導入後は、レッスンの品質が向上したと報告されています。
また、同社はAmazon Bedrockを用いてサポート対応の効率化にも成功し、対応件数を120%増加させました。
今後は多言語対応や講師のトレーニング強化にもAmazon Bedrockを活用する予定です。
事例3. 株式会社Works Human Intelligence
株式会社Works Human Intelligenceは、Amazon Bedrockを活用して、タレント検索と社員紹介文生成機能「Bizmatch」を開発しました。
その結果、個人情報を含むデータを安全かつ高性能で取り扱う新機能を短期間で実現しています。
AWSのPrototyping Programを活用し、開発が迅速に進みました。
今後、データガバナンス強化のためにAmazon Bedrock Guardrailsを導入し、業務負荷を軽減する予定です。
また、AIエージェントを活用した人事業務の自動化や、小規模言語モデルの活用も計画しています。
事例4. タキヒヨー株式会社
タキヒヨー株式会社は、Amazon BedrockとオープンソースのGenerative AI Use Cases JPを活用して業務効率化を実現しました。
4部門で月450時間の工数削減を達成し、デザイン部門ではTシャツのグラフィック製作をAIで大幅に効率化しています。
営業部門では貿易用語の理解が容易になり、資料作成の負担も減少しました。
EC部門では自分でサイト設定や分析ができるようになり、法務部門でもAIを活用した効率化が進んでいます。
今後、AIの活用をさらに広げ、業務の効率化とサステナビリティの向上を目指しています。
事例5. KDDI株式会社
KDDIは、AWSを活用してデータ基盤の刷新を進め、フロントシステムと基幹システムのデカップリング層「JOINT」を構築しました。
その結果、柔軟性とスケーラビリティが向上し、Oracle DatabaseからAmazon Auroraへの移行で運用コストが半減した効果が得られています。
処理能力が最大8,000トランザクション毎秒に向上し、バッチ処理時間が1時間から20分に短縮されました。
さらに、マルチリージョン構成を採用し、「止まらないAPI」を実現する環境作りを進めています。
AWSで役立つ資格

ここでは、AWSで役立つ資格を7つご紹介します。
初級レベル:AWS認定Cloud Practitioner
AWS認定Cloud Practitionerは、AWSの基礎的な知識を証明する入門レベルの資格です。
IT初心者やビジネス職向け**に設計されており、エンジニアでなくても取得できます。
AWSの主要サービス、クラウドの基本概念、料金体系、セキュリティ、運用モデルなどが学べます。
AWSを初めて学ぶ方やクラウドの概念を理解したい方、エンジニア以外のビジネス職の方、AWSの上位資格を目指す方におすすめです。
中級レベル:AWS認定Solutions Architect
AWS認定Solutions Architectは、AWSの設計・構築に関する知識を証明する資格です。
AWSのベストプラクティスを理解し、コスト効率が良く、セキュアでスケーラブルなアーキテクチャを設計するスキルを持っていることを証明できます。
クラウドエンジニア・インフラエンジニア向けで、AWSの主要サービスを理解し、最適なアーキテクチャを設計できることが求められます。
AWSの認定資格の中でも、特に人気が高く評価が高いです。
クラウドエンジニア・インフラエンジニア以外に、AWSを業務で活用している方やAWSの設計・構築に関わる職種の方、AWS認定Cloud Practitionerを取得し次のステップを目指す方に適しています。
中級レベル:AWS認定Developer
AWS認定Developerは、AWSを活用したアプリ開発に関する中級レベルの資格です。
ソフトウェアエンジニア・クラウド開発者向けで、AWS SDK、Lambda、API Gateway、DynamoDB、CI/CD(継続的インテグレーション/デリバリー)などが試験範囲となっています。
クラウドアプリ開発者やバックエンドエンジニア、フルスタックエンジニア、AWSを業務で活用している方、AWS認定Cloud Practitionerを取得し次のステップを目指す方におすすめです。
中級レベル:AWS認定SysOps Administrator
AWS認定SysOps Administratorは、AWS環境の運用・管理に関する中級レベルの資格です。
システム管理者・クラウドインフラエンジニア向けで、AWS環境の監視、障害対応、セキュリティ管理、パフォーマンス最適化が試験範囲となっています。
システム管理者やクラウドインフラエンジニア、ネットワーク・セキュリティ担当者、AWSを業務で運用している方、AWS認定Cloud Practitionerを取得し次のステップを目指す方におすすめです。
中級レベル:AWS認定 Data Engineer
AWS認定 Data Engineerは、AWS上でのデータエンジニアリングに関するスキルと知識を証明する中級レベルの資格です。
データの取り込み、変換、データパイプラインのオーケストレーション、データモデルの設計、データライフサイクルの管理、データ品質の確保などの能力を検証します。
データエンジニアリングやデータアーキテクチャの分野で2~3年の経験を持ち、AWSサービスの実践的な使用経験が1~2年程度あるプロフェッショナルが対象です。
上級レベル:AWS認定Solutions Architect
AWS認定Solutions Architectは、AWSのアーキテクチャ設計に特化した上級レベルの資格です。
AWSクラウド環境における高度なインフラ設計、デザインパターン、運用の最適化に関するスキルを証明します。
クラウドアーキテクチャの設計に関する深い知識と実践的なスキルが求められ、AWSのサービスや技術的な選択肢を使って複雑な要件に応じたソリューションを設計する能力を身につけられます。
AWSを利用してアーキテクチャ設計を行っている、もしくは行いたい上級エンジニアやアーキテクトにおすすめです。
上級レベル:AWS認定DevOps Engineer
AWS認定DevOps Engineerは、AWS環境におけるDevOpsのスキルと知識を証明する上級資格です。
AWSを使用したインフラの自動化、運用の最適化、CI/CDパイプラインの設計・管理など、DevOpsの実践的なアプローチを学び、実証することを目的としています。
DevOpsエンジニアやシステム管理者、AWS環境での自動化と運用の効率化に関心のあるエンジニア、AWS認定Solutions Architect – Associateを取得した後にDevOpsの実践的スキルを証明したい方が対象となっています。
まとめ
AWSは、柔軟かつ包括的なクラウドサービスを提供するプラットフォームです。
初期費用がかからず、運用コストの最適化が可能なので、予算が限られている企業や初期費用を抑えたい企業に適しています。
またグローバル展開の容易さや高いセキュリティが特徴で、幅広いユーザー層に使用してもらうシステムを開発・移行したい企業にもおすすめです。
AWSを使えば、サーバー環境の構築・運用、データ保存、コンテンツ配信、データベース管理、システム開発、IoTソリューションの構築、AI機能の活用など、幅広い使い方を実現できます。
