システム運用監視で防げるリスクとは?監視体制を整えるポイントや注意点を解説
システム運用監視とは、ITシステムが正常に稼働しているか監視する作業です。
システム上で問題が発生しても、監視により即座に発見されれば、すぐに対処できます。
本記事では、システム運用監視の対象や目的をはじめ、システム運用監視で予防できるリスクや監視体制を整えるポイントをご紹介します。
そのほか、システム運用監視の注意点もお伝えするので、監視体制を整えたい場合はぜひ参考にしてください。
目次
システム運用監視とは?

システム運用監視とは、ITシステムが正常に稼働し続けるように監視する活動です。
システムの動作速度やリソースの使用状況を監視し、異常があれば警告を出す役割があります。
そのほか、システムやサービスが稼働しているかダウンタイムがないか確認したり、不正アクセスや攻撃の兆候を監視してシステムの安全を守ったりするのも主な役割です。
運用監視は、障害の早期発見や迅速な対応、システムの最適化につながるため、安定した運用を維持するために不可欠な作業です。
監視する対象
システム運用監視の監視対象は、ITシステムが正常に稼働し、サービスを提供し続けるために重要な要素を広範囲にわたって監視します。
主に以下のポイントを監視します。
- サーバー
- ネットワーク
- アプリケーション
- データベース
- セキュリティ
- ストレージ
サーバーの負荷やリソースの利用状況を監視し、パフォーマンス低下やリソース不足の予兆を早期に発見するのが役割の1つです。
サーバーが正常に稼働しているか確認し、再起動が必要な場合に警告を出します。
ネットワークの監視では、帯域幅やネットワークの遅延、パケットロスを監視し、トラフィックの異常を検知します。
ネットワーク機器の接続状態を確認し、接続が途切れることなく安定しているか監視するのも作業の1つです。
さまざまな監視対象を包括的に管理することで、システム全体の安定性や信頼性を確保し、問題発生時に迅速に対応できるようになります。
監視する目的
システム運用監視の監視目的は、ITシステムが安定的かつ効率的に運用され、サービスが中断なく提供されることを確保することです。
システムの状態を常に把握し、異常や問題を早期に検知して対応することが含まれます。
システムが常に正常に動作しているか確認し、ダウンタイムやサービスの停止を最小限に抑えるのが主な目的です。
サーバーやネットワーク、アプリケーションが適切に稼働しているかを監視し、障害の予兆を早期に発見するのも目的の1つです。
システム運用監視の最終的な目的は、システムの安定稼働を維持し、サービスの品質を向上させ、ユーザーや顧客に提供する価値を最大化することといえるでしょう。
システム運用監視で予防できるリスク

システム運用監視では、さまざまなリスクを回避できる可能性があります。
ここでは、システム運用監視で予防できるリスクを4つご紹介します。
リスク1. 大規模障害への発展
システム運用監視の目的は、システムの異常や問題を早期に検知し対応することです。
その結果、大規模な障害に発展する前に問題を修正し、サービスの中断やデータ損失を防げます。
例えば、システム監視ツールは、サーバーやネットワークの異常、アプリケーションの動作不良などをリアルタイムで監視し、異常が発生した際には即座にアラートを発します。
これにより、大きな問題に発展する前に速やかに対処が可能です。
また、定期的なシステムチェックやパフォーマンス監視により、予期しない問題を未然に防止できます。
リソースの利用率が高い場合、容量の増加や負荷分散を事前に行うと、システムが過負荷で停止するリスクの低減が可能です。
リスク2. 夜間や長期休暇中の対応の遅延
システムは24時間365日稼働しているため、夜間や長期休暇中にも障害や問題が発生する可能性があります。
これらの時間帯に対応が遅れると、サービスが停止してしまったり、顧客に影響を与えたりするリスクが高まります。
運用監視を強化すると時間帯関係なく発生した問題に迅速に対応し、リスクを最小限に抑えられるでしょう。
監視ツールによっては異常が検出された時点で、関係者へ自動で通知を送る機能があります。
その結果、夜間や休暇中でも迅速に状況把握ができ、対応が遅れるのを防止が可能です。
リスク3. サーバーダウンによりシステム停止
サーバーダウンは、システム全体の稼働に深刻な影響を与え、サービスの中断や顧客への影響を引き起こします。
未然に防ぐためには、適切な監視体制が重要です。
システム運用監視を実施すると、サーバーダウンを事前に検知し、迅速に対応できるようになります。
CPUの使用率が90%以上に達した場合やディスクの空き容量が不足している場合、監視ツールはアラートを発信し、担当者が即座に対応できるようにする仕組みを取り入れると良いでしょう。
また、サーバーの動作が遅くなる、エラーが頻発する、メモリやCPUの使用率が高い、ログファイルに異常なエントリが記録されるなどの予兆があれば、早期に発見して問題が大きくなる前に対処するのが重要です。
リスク4. ビジネス機会の損失
サーバーダウンやシステム障害は、ビジネスにとって致命的な影響を及ぼす可能性があります。
オンラインショップや金融サービス、SaaSなどのサービスがダウンすると、顧客の取引ができなくなり、収益の損失や信頼性の低下につながります。
システム運用監視を実施することで、サーバーやアプリケーションの障害を迅速に検知し、問題が大きくなる前に対応するのが可能です。
例えば、オンラインショップの在庫管理システムや決済システムに障害が発生している場合、リアルタイムでアラートを受け取ると、即時に問題を解決して顧客が購入できるようにします。
その結果、顧客の購入機会を失うのを防止できます。
システム運用監視の体制を整えるポイント
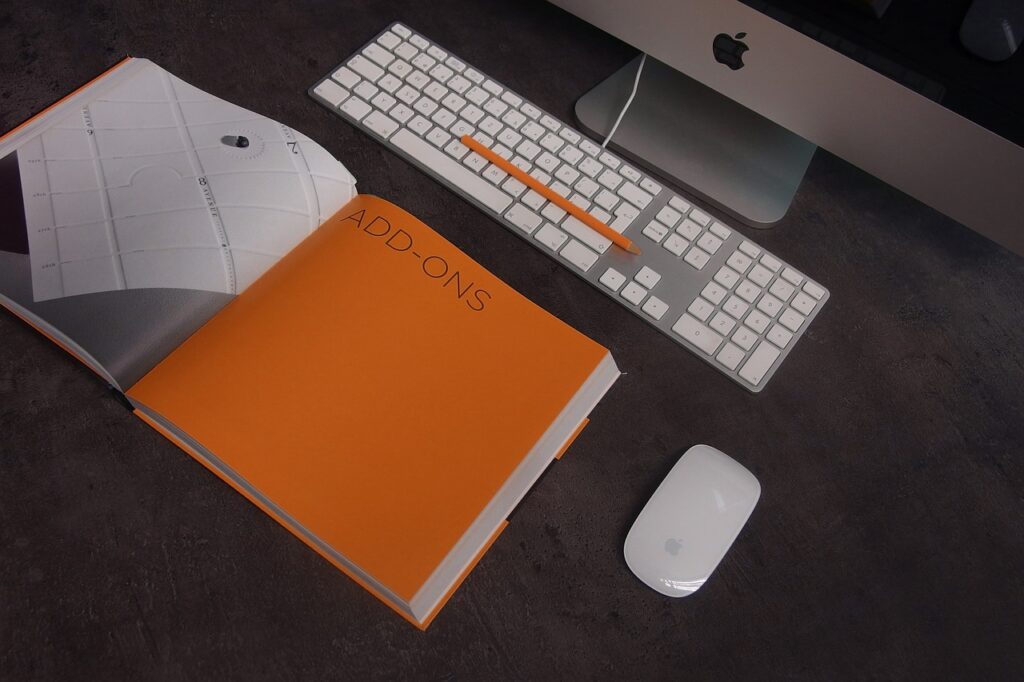
システム運用監視の体制を充実させるために、ポイントを押さえておきましょう。
ここでは、システム運用監視の体制を整えるポイントを6つご紹介します。
1. 監視方針を決める
監視方針は、システム運用監視がどのように行われるべきか、どのような基準で監視対象や対応が決定されるか明確にするための指針です。
適切な監視方針を決めると、システムの安定稼働を維持し、問題発生時に迅速かつ効果的な対応が可能になります。
監視対象となるシステムやインフラ、アプリケーションを特定することが重要です。
監視対象としては、サーバー、ネットワーク、データベース、アプリケーションのパフォーマンス、セキュリティ、ログ、サービスの可用性などがあります。
どの部分を監視するか明確にし、それぞれの重要性や優先度に応じて監視範囲の決定が求められます。
2. 情報収集やシステム構成の確認を徹底する
情報収集やシステム構成の確認を徹底すると、システム全体の状況を正確に把握し、問題発生時に迅速かつ効果的な対応が可能です。
システム運用監視を行う上で、最初に必要なのはシステム全体の構成を把握することです。
システム構成とは、サーバー、ネットワーク機器、ストレージ、ソフトウェア、インフラの関係性など、システムを構成する各要素の相互関係を指します。
構成を正確に把握すると、どの部分がどのように影響しあっているかを理解でき、問題が発生した際に迅速に原因を特定できるようになります。
システムに変更を加える際、変更内容や影響範囲を把握するのが重要です。
運用中にどんな変更が行われ、どの部分に影響を与えたかを記録しておくと、監視中に異常が発生した場合、変更内容が原因となる可能性を素早く確認できます。
3. 障害対応の流れを決める
障害が発生した場合、対応の流れを明確に定義しておくのが重要です。
障害対応プロセスは、障害が発生した瞬間からサービス復旧までの全てのステップを含みましょう。
検知から報告と振り返りまでの流れを細かく定義し、誰がどのタイミングで何を行うべきか決めておきます。
また、障害対応の際に誰がどのような役割を果たすかを明確にしておくのが重要です。
役割分担を明確にすると、無駄な混乱や遅延を避け、スムーズな対応が可能になります。
4. 監視ツールを実装する
監視ツールの選定は、システム運用監視体制の成否を左右します。
監視対象や監視目的に応じたツールを選定するのが重要です。
システム運用監視に使われる監視ツールには、インフラ監視ツール、アプリケーション監視ツール、ログ監視ツール、ネットワーク監視ツール、クラウド監視ツールなどの種類があります。
適切な監視ツールを選定し、監視項目を設定すると、システムの健全性を維持し問題を早期に発見して対応するのが可能になります。
ツールを運用しながら定期的に改善を加えていくのも、システムの安定性を保つために不可欠です。
5. ドキュメンテーションの管理を徹底する
ドキュメンテーションは、システム運用監視におけるさまざまな情報を記録し整理しましょう。
運用担当者が変わった場合でも、ドキュメントに基づいた対応ができるようになり、監視業務の継続性が保たれます。
障害発生時に、過去の事例や対応手順を参考にすると、素早く問題解決につながる可能性が高まります。
チーム全体での情報共有が可能となり、運用スキルの向上や標準化が進むでしょう。
ドキュメントの管理方法としては、中央管理とバージョン管理を徹底し、定期的なレビューを行いながら、運用に役立つ情報を整理するのが求められます。
6. アラートを確認する
アラートは、システム運用監視ツールから発生する警告で、監視対象のシステムやサービスに異常が発生したことを示します。
具体的には、CPU使用率の急増、メモリ不足、ディスク容量の枯渇、ネットワーク障害など、運用中の問題をリアルタイムで知らせるために使われるのが一般的です。
アラートが発生すると、運用チームがすぐに対応できるよう、異常を知らせる通知が行われます。
通知を適切に受け取り確認すると、迅速な問題解決やリスク回避につながります。
アラートには緊急度が異なるものがあり、すべてのアラートが同じ重要度を持つわけではないため、適切に分類し、優先度を設定するのが必要です。
アラートが発生した際に、どのように通知を受けるか決めておきましょう。
通知方法は、メール通知、SMS通知、ダッシュボード通知、チャットツール通知があります。
通知を受けた担当者がすぐに確認できるよう、適切なツールや手段を選定し、アラートを管理する仕組みを整備しましょう。
システム運用監視の注意点

システム運用監視の体制を整える上で、いくつか注意点も把握しておくのが大切です。
ここでは、システム運用監視の注意点を2つご紹介します。
注意点1. 専門知識を持つ人材を確保しなければいけない
システム運用監視を効果的に行うためには、システムアーキテクチャの理解、運用ツールの知識、トラブルシューティング能力、セキュリティの知識などの専門知識が必要です。
異常が発生した際に、原因を迅速に特定し、適切な対応をするためには高度な知識と経験が重要です。
特に、システムの停止やサービスのダウンタイムを最小限に抑えるためには、専門的な判断が求められます。
障害が複合的な原因によって引き起こされている場合、単純な解決策では対応できません。
ネットワークの問題、サーバーの負荷、アプリケーションのバグなど、複数の要因が絡み合う障害に対応するためには、幅広い技術的な知識が必要です。
注意点2. 定期的なマニュアル整備が必要である
マニュアルには、システム運用や障害対応の手順、定期的な監視内容、トラブルシューティング方法などが明記されているため、担当者は状況に応じて正確で一貫した対応ができます。
定期的に更新されたマニュアルを使用すると、スタッフ全員が同じ基準で作業を行い、効率的な運用が可能となります。
システム障害が発生した場合、手順書やマニュアルが整備されていると、担当者は状況に応じた対応が可能です。
障害が深刻になる前に、定められた手順に従って適切な対応を取れれば、ダウンタイムを最小化できます。
システム運用担当者が入れ替わる際や新しいメンバーが参加する際、最新のマニュアルがあれば、新規担当者にとってもスムーズに業務を引き継げます。
マニュアルが整備されていれば、担当者が過去の事例や運用手順を確認しながら業務を学べるため、教育の手間が省けるでしょう。
まとめ
システム運用監視は、システムの稼働状態を常に監視し、トラブルやリスクを予防するための重要な活動です。
監視の対象にはサーバー、ネットワーク、アプリケーションなどがあり、目的は障害の早期発見と迅速な対応です。
運用監視により、大規模障害やシステム停止、ビジネス機会の損失といったリスクを軽減できます。
監視体制を整えるには、方針策定やツールの実装、障害対応フローの整備が重要です。
また、専門知識を持つ人材の確保やマニュアル整備も欠かせません。
